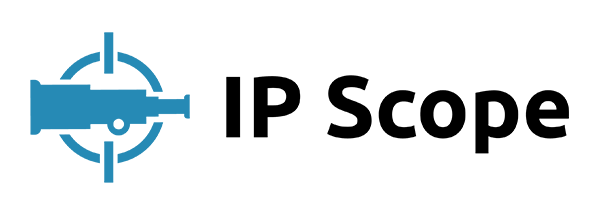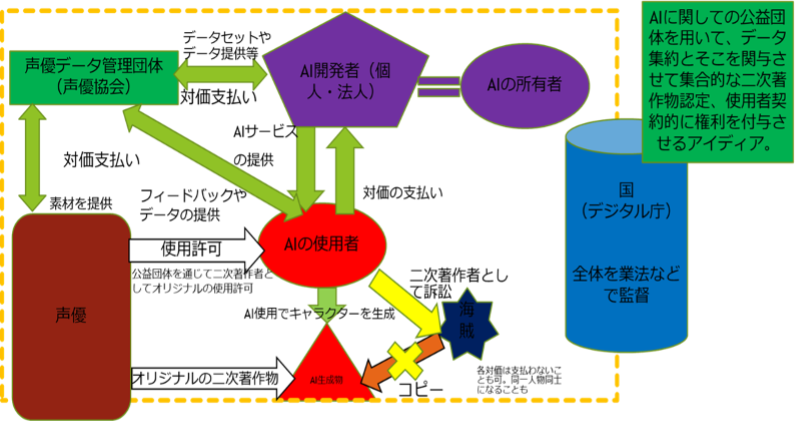AI生成物の利益還元モデル(後編)

※本コラムは、執筆者の私見によるものであり、所属団体その他の見解を代表するものではありません。また、執筆者の過去学会発表・論文・書籍・ブログなどですでに発表済みの内容を再編集しています。
IP Scopeの狙いは、特許をはじめとする知財に関する情報を分析することによって、技術動向や今後の予想、企業の技術戦略を見つけ出すことにある。ビッグデータ時代である現在は、データ分析によって新たな知見を見出し、それを企業の戦略やオペレーションに活かすことが重要になってきている。
一方、特許という技術分析のみで企業の戦略やオペレーションを立案することは危険である。「ルール形成」という分野があるように、現状の問題点を把握して、「標準化」なども組み合わせて新しい「ルール」を作っていくことをリードする必要性も時には生ずる。
このコラムでは、NBIL-5による環境やテクノロジーの最新状況分析を踏まえ、それぞれの分野の動向や課題を明らかにしていく。
第30条の4について、さらに詳しく解説
前回、AI 生成の学習データに関して、構造的問題を解説した。前回解説しきれなかった第30条の4について、さらに詳しく解説したい。筆者は、この立法がホールドアップ問題への対応を含む政策的配慮に基づくものと理解している。
まず、不完備契約理論がある。技術進歩による契約の不完備性の指摘だ。具体的には下記となる。
従来の著作権契約とAI学習の課題
1. 従来契約の限界
・従来の著作権契約は AIによる学習利用を想定していない。
・「予見不可能な技術使用」への対応が不足している。
・契約時点で 将来の使用形態を規定するのは困難。
2. ホールドアップ問題の発生
・この空白から ホールドアップ問題 が生じる。
・(著作権法30条の四により、一定程度は解決できる部分もある。)
3. 時系列での流れ
t=0:著作者が作品を創作・公開
t=1:AI技術が発展
t=2:AI企業がデータ学習に作品を利用
t=3:著作者がその使用を発見
4. 問題の本質
t=0時点では将来のAI利用を予見し、契約に明記することが難しい。
その結果、交渉力の非対称性 が発生する。
ホールドアップ問題をAI利用の文脈で整理する
1. ホールドアップ問題とは
▶︎定義:一方が先に投資(沈没費用)を行った後、相手方がその弱みに付け込み、有利な条件を要求する問題。
・ポイント:一度費やした時間・労力・コストは取り戻せず、交渉で不利な立場に置かれる。
2. 時系列で見る流れ
t=0:作品の創作
・著作者が時間と労力をかけて作品を制作。
この時点では AI学習への利用は想定されていない。
・沈没費用:創作に投入した資源は回収不能。
t=1:AI技術の発展
・AI技術が急速に進化。
・過去に創作された作品が、突如として「AI学習に価値あるデータ」となる。
t=2:AI企業による学習利用
・AI企業が、過去の作品を学習データとして使用開始。
・著作者は事前に同意していない。
t=3:発覚と交渉
・著作者が自作の利用を発見。
・この時点で初めて交渉が始まる。
3. 問題の本質
t=0時点では、将来のAI利用を契約に明記することが難しい。
そのため、後になって利用が判明すると 交渉力の非対称性 が生じやすい。
結果として、ホールドアップ問題が発生する。
この問題を、30条の4は著作者側では無くAI企業側に立ったホールドアップを問題視したのだろうと思われる。
AI企業側に立ったホールドアップ問題と30条の4
AI企業の弱い立場(加害者側のホールドアップ)
AI企業の状況
・沈没費用:数十億円規模の開発費用をすでに投入済み。
・撤回困難:学習済みモデルから特定作品の影響だけを除去することは技術的に困難。
著作者の立場
・交渉力:「私の作品を使うなら高額な対価を払え。嫌なら全部作り直せ」と要求可能。
・結果:特に有名著作者は、過剰に高い対価を要求できる立場になる。
▶︎立法趣旨との関係
このような「AI企業が交渉で不利になるホールドアップ」を回避するために、30条の4が導入されたと理解すると分かりやすい。